事務所通信7月号
経営:黒字経営への道しるべ(第1回)「社長の成績表」変動損益計算書を見てみよう!
見込んでいた儲けの額と、決算書や損益計算書上に表示される
「売上総利益額」の数字とに差がある――と感じたことはありませんか?
このような場合、変動損益計算書を利用することで、
頭の中でイメージしていた利益構造と実際の数字とを一致させることができます。
変動損益計算書は、すべての費用を売上高に伴って増減するか否かで
「変動費」と「固定費」とに分けて表示した損益計算書で、
売上の増減で限界利益がどれくらい変わるかが把握しやすくなる、などの特長があります。
また、変動損益計算書は社長の意思決定の結果が表れる「社長の成績表」ともいわれ、
①自社の製品やサービスが顧客や市場に評価された結果
②儲けの範囲内で経費をどのように使ったか――が表示されます。
7月号から開始の全6回連載「黒字経営への道しるべ」では、
「いま、自社に何が起きているのか?」を読み取り、
次の打ち手を考えるために欠かせない変動損益計算書のポイントについて解説していきます。
消費税:インボイス制度3か月前対策 自社のインボイスは要件を満たしていますか
インボイス制度への対応はお済みでしょうか。
制度開始を目前に控えたいま、
自社がインボイスとして発行する請求書等に記載事項のモレがないかあらためて確認しましょう。
インボイス制度では、現在、使用している請求書等(区分記載請求書等)に、
①登録番号(「T」+13桁の数字)②適用税率③税率ごとに区分した消費税額等――
の記載が必要です。記載事項にモレがないかを確認しましょう。
いわゆる「レシート類」の簡易インボイスには、
上記①および②③のいずれかの記載が必要になります。
インボイスに記載する氏名・名称等は、屋号や省略した名称でも構いません。
ただし、電話番号を記載するなど、インボイスを発行する事業者が特定できることが必要です。
なお、インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」について生じる
1円未満の端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は、事業者の任意で決めて構いません。
ただし、端数処理は1つのインボイスにつき、税率ごとに1回のみとされています。
事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!
一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。
同制度を利用するには、
令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、
令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。
令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、
その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。
そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。
特例承継計画の作成・変更には、
税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。
以上の記事について詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!
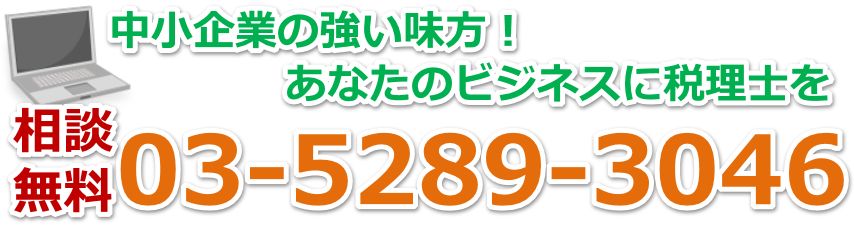

お問い合わせフォーム